右肩上がりの人気を誇る東京湾のサワラキャスティング。シーンのスタートとともにハマったという上屋敷隆さんに、東京湾ならではの愉しみ方、タックルセレクト、実釣時の注意点などをお聞きした。神出鬼没なサワラを確実に仕留めるためのノウハウ、ぜひ身に着けていただきたい。
東京湾サワラキャスティングとは?

日本のソルトルアー黎明期から活躍している上屋敷隆さん。ショア、オフショアのあらゆる釣りに精通しているが、サワラキャスティングもしっかりハマった釣りのひとつだ。
上屋敷さんと東京湾サワラキャスティングとのお付き合いは?
 上屋敷隆
上屋敷隆東京湾でサワラキャスティングが始まった当初は、ナブラ撃ちがメインパターンだったんです。僕はそこからスタートしています。
ナブラ撃ちって楽しいじゃないですか?夏のカツオやマグロ釣りのような釣りが、ライトなPE2号タックルで 楽しめる、しかも冬に!っていうのがハマったきっかけですね。
近年の東京湾ではブレードジギングが主流になっているので、ナブラをミノーで撃つという釣りの割合は少なくなっていますけどね。
シーズンも以前は冬から春にかけてが中心でしたが、最近は9月、10月がベストシーズンという印象。サイズに関しても3kg、4kgといったサワラに加えて、サゴシクラスの数が増えてきたように感じますね。


ミノーやペンシルなどを使ったナブラ撃ちのキャスティングゲームから始まった東京湾のサワラキャスティング。ブレードジギングが主流となった現在でも、ナブラ撃ちへのこだわりが強いのが上屋敷さんのスタイルだ。
ブレードジギングの魅力はどのように感じている?



僕が感じているブレードジギングの魅力、面白さは、ヒットしたときのアタリですね。
ガツンッと来る衝撃がサイズの割には大きい。ライトタックルということもあって、ワクワクする一番の要因ですね。
独特なサワラの引き方もいいですよね。意外とやり取りにテクニックが必要なんです。
縦横無尽に引いて暴れまくるので、しっかりしたロッドワークが必要。船の際に来てからのツッコミでバラす、っていうことが多いので難しさもある。だから面白いんですけどね。


バイトの衝撃が面白さ、と上屋敷さん。東京湾でのブレードジギングではタチウオは常連ゲストのひとつ。
東京湾サワラキャスティングでは船の選択肢が多い
東京湾ならではのサワラキャスティングの特徴は?



東京湾のサワラキャスティングの特徴として、大型乗合船と小型のチャーターボート、2つを選択できる点にあると思います。
乗合船の場合は、いろいろなお客さんがいるので勉強にもなりますよね。 なんであの人ばかり釣れるんだろう?、巻きのスピードはどのくらいかな?、あの色で喰っているな、とか。釣果の差と理由が分かりやすい。
毎週来ている人を見ていると、やはり動きに無駄がないですからね。ハリ先チェックしてケアしているとか。細かいことやっているなっていうのは、見ていて勉強になりますよ。


上屋敷さんも足を運ぶという深川・吉野屋のサワラキャスティング船。このクラスの大型乗合船で気軽にサワラキャスティングを楽しめるのは、東京湾の魅力のひとつ。



大型乗合船でブレードジギングをする場合、基本的に両舷に乗っての釣りになります。
風上の舷、ラインが払い出している方向の釣り座ではルアーが浮きやすいので、引いてくる間に1回か2回、着底し直してレンジキープするように心掛けるのが基本。
風下側の舷、ルアーに近寄っていく方向の釣り座では、ラインがどんどん弛んでくるので1回の着底でピックアップするような感じに引いてくるのが基本。
もちろん、水深によって多少変わります。
でも、釣れ方は両方とも同じような感じになることが多いです。どちらの舷であっても引き抵抗の変化に合わせて、ベストなスピードを探っていけば答えが出やすいと思います。
また、大型乗合船では水面からの高さがあるので、釣り座によってはブレードジグなどは結構浮いちゃう。最後まで引き切るにはロッドティップをしっかり下げるなどの工夫が必要ですね。


今回、撮影でお世話になった横浜のサニーフィッシングガイドサービス。軸足をシーバスに置きながらシーズンになればサワラも狙う。こうしたスタイルが同船、また一般的な東京湾のチャーターボートの立ち位置だ。
東京湾では全国的にも主流となっている小型ボートでも楽しめる。



小型のチャーターボートは水面までの距離、つまり魚との距離が近い点も面白さですね。
基本的に仲間同士でチャーターする楽しさもある。仲間がいれば、みんなでいろいろなことが試せるので、釣果アップにもつながると思います。
機動力もあるので、突然ナブラが出た場合でも、そこに向かって走っていってミノーの釣りにスイッチできます。これは乗船者が多くて船体が大きい大型遊漁船ではなかなか出来ない動きですね。
ブレードジギングも好きだけど、ミノーキャスティングでのナブラ撃ちはもっと好き、という方は、チャーターボートで楽しむのもおすすめですね。
キャスティングスタイルによるPEのセレクト術


ミノーキャスティングには「アバニ キャスティングPE マックスパワー X8」、ブレードジギングには、「アバニ ジギング10×10マックスパワーPE X9」というのが上屋敷さんのセレクト。
東京湾サワラキャスティングで使用しているメインライン、まずはブレードジギング用には何を使っている?



ブレードジギング用には「アバニ ジギング10×10マックスパワーPE X9」を使用しています。強さはまったく問題ない、余裕の合格点。
使っていて一番気に入っているところは水切れがいいところ。これは明らかに感じられますね。水から上がってくるときに水を引き連れてこない。
ちょっとした衝撃で水が弾け飛ぶっていうのが見えますし。水中でも同じでしょうから、この性能は感度の良さに直結すると思いますよ。


大前提となる強さは言わずもがな、という上屋敷さん。「アバニ ジギング10×10マックスパワーPE X9」の使用感としては水切りの良さ、適度な張りがお気に入りだ。



適度な張りもいいですね。たるみも出にくいので、風があるときでもラインをさばきやすい。使いやすい、ラインさばきをしやすい、って重要じゃないですか。
ラインさばきが上手に出来ない人はトラブルが常につきまといます。トラブルを少しでも軽減してくれるラインなんじゃないかなと思いますね。
リーダーとの結節もやりやすいし、色落ちも少ない気がします。3回ぐらい使っても全然変わらないですね。
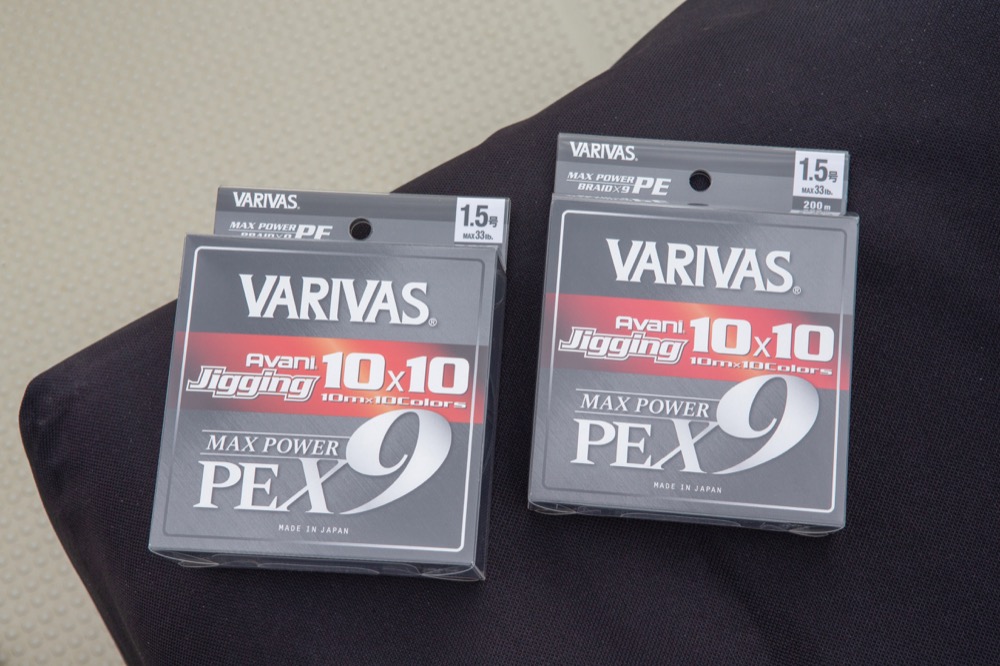
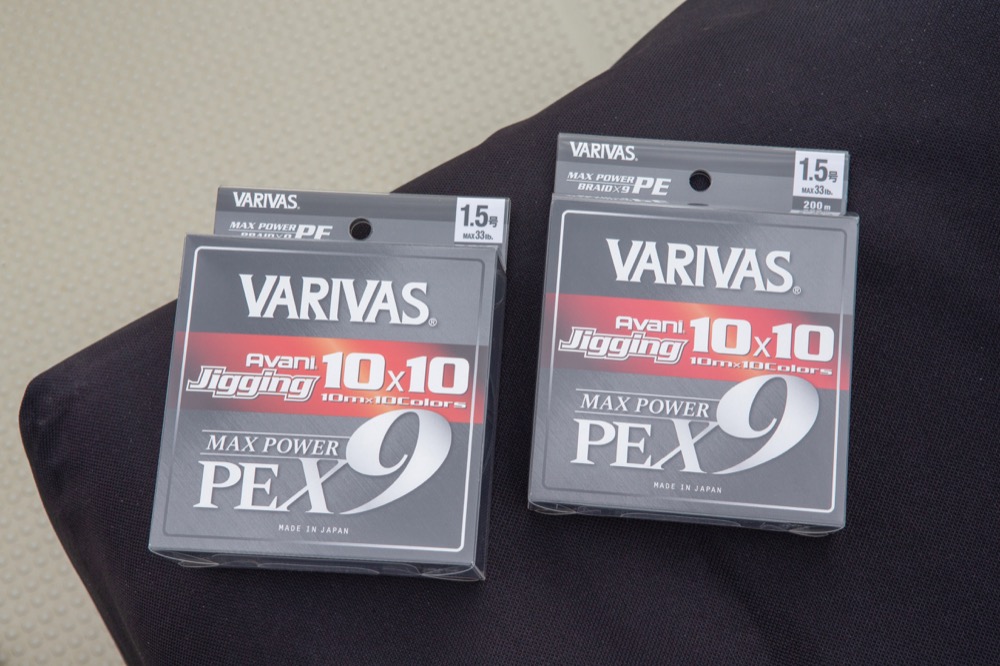
「アバニ ジギング10×10マックスパワーPE X9」の10×10ならではのカラー分けは、レンジを探る釣りとなるブレードジギングでは重宝される一面だろう。
ミノーキャスティング用のPEラインは?



ミノーのキャスティング用では「アバニ キャスティングPE マックスパワー X8」を使っています。
セレクト理由の一番は視認性の良さです。白色が凄く見やすい。これまで、このラインの2号はシイラやカツオキャスティングでかなり使い倒しました。
発売からずっと使っているので、信頼感は抜群です。変なところで切れたとか、そういうことはまったくない。しなやかだからノットも組みやすいですし。
今回は、シイラに使っていたスプールをそのまま入れてきただけなんですけどね。


PEにシュッ!は最初にスプールに巻き込むときのみに使用し、それ以外はほとんど使わない、という上屋敷さん。それで十分であり、ラインさばきに慣れている上屋敷さんは、これだけでエアノットなどに悩まされることはほとんどない、という。
リーダー素材の選択と長さなどのセッティング


リーダーセレクトの基本はジギングにはフロロカーボン製、キャスティングにはナイロン製を使うが、それだけに縛られる必要はない、と上屋敷さん。
使っているリーダーは?



ミノーキャスティング用にはオーシャンレコードショックリーダー、ブレードジギング用にはフロロカーボンショックリーダーを使っています。
基本的な考え方は、キャスティングでナイロン、ジギングではフロロという考え方でいいと思うんです。ただ、ちょっと自分が使っているロッドでは硬すぎるなって感じたら、ショック吸収力を期待してナイロンを使ってもいいんじゃないかなと思っています。
とくにサワラキャスティングでは、ヒットさせてからのサワラの不規則な動きに対応し、バラシを減らすためにも、多少伸びてくれるナイロンを使った方がいいときもあると思います。このあたりは臨機応変でいいと思いますよ。
長さとしては2ヒロ(約3m)をスプールから出して、ノットを組み終わった最終的な長さが1ヒロ半(約2m強)くらいになるようにしています。
ノット部分はベールと元ガイドの間にあるくらいで、スプールには巻き込んでいません。使っていくうちにカットしていって、最短で矢引き(約90cm)ぐらいになったら、システムを組み直す感じですね。


ルアー交換の利便性を考えてスナップを利用していた上屋敷さん。リーダーの傷みを考慮して頻繁に結び替えていたのが印象的だ。



ラインとリーダーの結節は、家で準備するときはPRノットです。現場で作るときはFGノットで組み直します。
現場ではいちいち道具を出していられないので、指でFGノットを作って対応しています。
ルアーとの接続はスナップを使っています。スナップとの結節は最初は巻き結びで、あとはハーフヒッチを1cmくらいになるように繰り返します。みなさん、ラーノットと呼んでいるノットですね。
東京湾サワラキャスティング用タックル


ブレードジギングがメインパターンとなることが多い東京湾では、ブレードジギング用2セット、ミノーキャスティング用に1セット、というのが上屋敷さんの基本セッティング。
東京湾でサワラキャスティングを楽しむには何セットのタックルが必要?



僕の場合、東京湾では3セットが基本になります。ブレードジギング用タックル2セット、ミノーなどのキャスティング用が1セット。3セットあれば十分だと思います。
ブレードジギングの場合、どうしてもタチウオがいたずらしてきて、ラインカットされちゃうときもあるので、やはり2セットは欲しいですね。
せっかくの時合にラインシステムを組み直す、ということは避けたいですから。タックルを持ち替えてすぐ投入できる状態をキープしておきたいですね。
どうしてもワンセットになってしまう、という方は替えスプールの準備をおすすめします。もし、ミノーキャスティングメインでも楽しめるよ、という状態だったら、ミノー用タックルを増やしていく、という感じで調整します。
ブレードジギングが主流になっている東京湾での、ロッド、リールのセレクト術は?



ブレードジギング用ロッドとしては、専用ロッドを選ぶのも一手ですが、まだ選択肢は少ないので、スーパーライトジギング、ライトジギング用ロッドで代用するのもいいと思います。
長さ的には6~7ftぐらい。注意点としてはあまりに張りの強い、硬いロッドは使わないほうがいいですね。ちょっと軟らかすぎるんじゃない、というくらいでも全然大丈夫。むしろそっちの方が乗せやすくて、バレにくい。
あとはグリップに注意ですね。ある程度の長さがあって、脇で挟んで固定して直線引きができるようなバランスがちょうどいいと思いますよ。


超高速巻きがブレードジギングの基本。リールの果たす役目が大きい釣りなので、4000番、5000番というサイズと、HG、XGというギア比にはこだわりたい。



ミノーキャスティング用のロッドの選択も意外に難しいんですよね。
専用ロッドもありますが、流用だったら7ftから8ftの間のシーバス用、ボートシーバス用、一番パワーがあるクラスがおすすめ。
8ftだと船体や釣り座によってはちょっと長すぎるかもしれませんけど、大型遊漁船だったら、8ftぐらいでも余裕で振れる船、釣り座もあります。
飛距離が出るし、足元まで引き切れるので有利なときもありますよ。シイラ用とかはちょっと強すぎますね。ほかにも一番軟らかいショア用の青物ロッドでもいいかも知れません。
リールはカタログスペック上、ハンドル1回転で1mくらい巻けるやつがいいですね。HG、XGといったハイギアモデルがおすすめです。
サイズは4000番、5000番。ミノーキャスティングに変わったとしても代用できますし。
メインラインに1.5号を巻いておけば、東京湾でやる分にはキャスティングもブレードジギングも両方できますよ。
上屋敷流・ルアーのセレクトパターンは?


ブレードジギングメインといってもナブラ撃ちに転じることは珍しくはない。常にブレ―ドジグとミノーは用意しておきたい。
ルアーはどのようなものを持参すればよい?



ブレードジグは40gをメインにしています。潮が速いときなどは50gも活躍します。
タングステン製だけでなく、シルエットが小さいものであれば一般的な鉛製のジグでもいいと思います。
個人的なこだわりとしては、フックを既製品のやつよりワンサイズ上げることですね。
目安としては2/0くらいにサイズアップします。しっかり掛かってホールドするのでバラシが少なくなります。
フックを大きくしたからといって動きが変わるとか、ブレードの回転が悪くなることはないと思います。


ブレードジグはサワラ、タチウオによるロストも多いので、準備は万端にしておきたい。



ミノーキャスティング用としてのスタンダードは、長さは12~13cm、20~40gのシンキングミノーですね。
ちょっとライトなものとして、9~10cmクラスで、20~24gのシンキングミノーも用意しておくといいと思います。あとは9~12cmのシンキングペンシルもおすすめ。
これらをいくつか用意すれば、ほとんどのキャスティングゲームはカバーできると思います。
いずれにしても、ある程度飛距離を稼ぐことができるシンキングタイプが基本です。


ミノーの基本はシンキング。飛距離性能と高速リトリーブでの泳ぎ、安定性などを重視して選択したい。
サワラキャスティングにおける注意点とアドバイス
東京湾のサワラキャスティングに関して、これから挑戦しようというアングラーに対し、何かアドバイスを!



個人的にはブレードジギングは斜めのジギングと考えています。そのうえで、船長の指示したレンジをいかに効率よく、そのストライクゾーンを長く引けるか、を常に心掛けています。
そのためにも自分が使っているリールはハンドル1回転で何cm、何m巻けるのかっていうことを理解し、なおかつラインカラーを見て、 自分のブレードジグがストライクゾーンを通っているのか、を考えながらやることが大切です。
自分のタックルのことをちゃんと知っておかなければダメ。そのリールはハンドル10回回すと何m巻けるの? って聞かれたら、すぐに答えられるくらいでないと。
それが分かって初めて、ハンドル10回巻いてまた落とす、20回巻いてまた落とす、そのどちらが有効か、ということが判断できるようになる。引くレンジが変わってきますからね。


釣り座によって潮の当たり方が変わるため、スピード調整することもヒットレンジを長く引くためのコツ。ブレードジギングでは基本的、かつ大切なテクニック。



あとアワセ方とやり取りですかね?
基本は巻きアワセ。バイトが来たからロッドをガッとあおるのではなく リールを巻いてアワせる。リールを巻いてグリグリってアワせて、リールで乗せる。
それからはロッドを曲げたまま、一定の速度でポンピングせずに寄せてくるという感じですね。サワラは船縁近くに来たら必ず突っ込むので、それにうまく対処できるようにしておく。
グリップエンドを腰や腹に当てないで、脇抱えの状態でファイトをする。
とくに大型遊漁船だと下に突っ込まれたりして、船縁に擦って切られちゃったりしますから。この場合は大きく前に乗り出すようなロッドワークが必要になります。
サワラとのファイトではロッドワークはとても重要です。


少し難しさのあるサワラとのファイトも魅力のひとつ、と上屋敷さん。確実なキャッチのためには、ショックを吸収してくれるロッドのセレクトと、臨機応変なロッドワークが求められる。
上屋敷隆さんの東京湾サワラキャスティング用タックル
上屋敷さんが東京湾サワラキャスティングで使用しているタックルは以下の通り。
ミノーキャスティング用タックル
| タックル | 詳細 |
|---|---|
| ロッド | マングローブスタジオ/ ブラックヘラクレス722S-L/TZ |
| リール | シマノ/ ステラC5000XG |
| ライン | 【バリバス】 アバニ キャスティングPEマックスパワーX8 2号 |
| リーダー | 【バリバス】 オーシャンレコードショックリーダー 35lb |
| ルアー | マングローブスタジオ/ストライクジャーク120S マングローブスタジオ/アトゥーラ90、120 シマノ/シュートジャーク125SP |
ブレードジギング用タックル1
| タックル | 詳細 |
|---|---|
| ロッド | シマノ/ グラップラー タイプ ブレードS70-0 |
| リール | シマノ/ ツインパワーC5000XG |
| ライン | 【バリバス】 アバニ ジギング10×10マックスパワーPE X9 1.5号 |
| リーダー | 【バリバス】 フロロカーボンショックリーダー 30lb |
| ルアー | シャウト/ブレードショーテル40g、50g シマノ/メタルショットTG32g、40g シマノ/タングマンブレード40g、50g |
ブレードジギング用タックル2
| タックル | 詳細 |
|---|---|
| ロッド | マングローブスタジオ/ ライトジギングロッド6.6ftプロトモデル |
| リール | シマノ/ ステラ4000M HG |
| ライン | 【バリバス】 アバニ ジギング10×10マックスパワーPE X9 1.5号 |
| リーダー | 【バリバス】 フロロカーボンショックリーダー 30lb |
| ルアー | シャウト/ブレードショーテル40g、50g シマノ/メタルショットTG32g、40g シマノ/タングマンブレード40g、50g |













