津軽海峡・龍飛崎沖の激流を泳ぐ大ダイ。この難敵にタイラバを駆使して挑むスタイルこそ、佐藤偉知郎さんが考える「海峡マダイ」。本記事では海峡マダイの魅力、さらには佐藤さんの使用タックルやセレクト術、激流の攻略術などを紹介していく。
佐藤偉知郎さんが考える、タイラバで狙う海峡マダイ

佐藤さんにとってタイラバで狙う津軽海峡のマダイの魅力とは?
アベレージサイズが大きいというところがまずありますね。
状況次第ですが数も出ます。そして何よりも引く魚が多い。津軽海峡の流れが一番速いところでやりますからね。
どんな魚でも流れの速いところにいるやつは引きますが、龍飛崎周辺のマダイはコンディションもいいんです。
シーズンを問わず、大きい魚が多くて食べても美味しいんです。
なぜ大きい魚が多くて食べても美味しいマダイが多いのか、と考えると、流れの中に常にいるやつって魚を多く食べているからだと思います。
湾内とか流れの緩いところに入ってしまうと、季節によっては海藻とか、貝を食べるようになってしまう。
そのために味の変化があるんだと思います。
海峡マダイに関しては、美味しくない時期がないというか、常にコンディションが良い。
魚体のコンディションの良さが流れの速さと相まって引きの強さにつながっているのかな、と思います。


龍飛崎周辺を狙う海峡マダイ、ポイントの特徴は?
龍飛崎周辺のポイントの特徴を教えてください。
潮が速いというのが一番の特徴ですね。4ノット、5ノットは当たり前、速い時は10ノット近くで流れます。9ノットとか8ノットも普通。
今日はちょっと遅いなって思うときで2、3ノット。速さもありますが、複雑さもあるのも特徴です。


ボトムの質や形状の特徴は?
ボトムの質はいろいろです。
岩盤のところもあるし、砂のところもあるし。龍飛崎沖の馬の背に向けて流し始めるところはだいたい砂地。
だんだん浅くなってくると岩盤が出てきて、さらに剣山みたいな岩というか岩盤みたいなのがあって、そこを超えると岩盤絡みの砂地になる、そんなイメージですね。


水深は大体どのくらいですか?
おおよそを言うと40mから70mぐらい。
水深50mで、ラインを100m出さなければ着底しないときもあります。140m出しても取れなかった時もありましたね。
素直な二枚というんですか、それぞれの流れに角度がない二枚潮だったら底が取れるんです。
だけど、角度がある二枚とか、三枚になったりしてくると、本当に底が取れない。
要するにタイラバは止まっていてもラインは出ていく状態です。
ラインが出ていくスピードに変化があれば底が取れますが、出方に変化がない時もある。
そうなると、ボトムタッチがなかなか難しいし、タイラバのロストもすごく多くなるんです。


海峡マダイでメインとなるベイトは?
イワシ類が多いと思います。龍飛崎周辺の深場には常にイワシがいるんです。
その群れが潮の動きに連動して動き、マダイも一緒に動いているような気がします。
イワシも何種類かいます。ウルメイワシもいます。あとはいわゆるモジャコ(ブリの幼魚)アジ、サバ、いろいろな小魚ですね。
いままでサイズはどのくらいまでキャッチされているんですか?
僕は釣ったことはないですが、90cmオーバーは何枚も出ていると思います。
自分の記録は87cmです。
このサイズが流れに乗ったらなかなかの引きですよ。船でフォローしてもらわないと獲れない、そんな感じです。


海峡マダイのシーズンを教えてください。
海峡マダイに関して言うと季節は問いません。出船できればいつでもシーズンです。いなくなることがないんです。
おそらくエサを食えるからだと思います。
強くて大きい魚はいつでも激流の中に残ることが出来るからだと思います。
すごくたくさん釣れる時とか、釣れない時とかというのはありますけれど、釣れないシーズンはないんですよね。


海峡マダイを狙うための佐藤偉知郎流タックル|ロッド&リール
タックルセレクトのヒント、まずはロッドから教えてもらえますか?
ロッドはまずタイラバの重さを背負えることが第一条件。
ソリッドティップの先調子のロッドは使いにくいですね。
全体が曲がってタイラバを背負ってくれるような、少しパワーがあるもの、オールチューブラーのロッドが向いていると思います。
軽いタイラバしか背負えないような、鋭敏なタイプはちょっと不向きです。
リールについてはどのようなものがおすすめですか?
リールは壊れにくいことが第一。とくにクラッチですね。
クラッチを切ったり入れたりの回数が半端ではなく多いからです。
1回落として巻き上げるまでに何十回もクラッチを切って落として。また切って、ということもあります。必然的にクラッチの耐久性が高いものがいい、となります。
ある程度の巻き上げトルクも欲しいですね。
さらにドラグもちゃんと効くというのが最低条件です。
そう考えてくるとあまり安いものはおすすめできません。


メインに使っているのは100番。ギア比の低いトルク重視のタイプです。
巻き上げの速度は遅いですけど疲れにくい。楽だという点、トルクがあるという点が利点です。
サイズ的に下巻きせずに1.5号が200mちょうど巻き込める。
PEラインが無駄にならないといったコスパのよいところも長所です。
ただ、深い場所に行ったり、ちょっと潮が速すぎてタイラバが流されて、100番だと巻き上げが遅すぎる、という時は、300番のハイギアタイプを使うこともあります。
海峡マダイを狙うための佐藤偉知郎流タックル|PEライン&ショックリーダー
使用しているPEラインについて教えてください。
具体的にはバリバスのアバニ ジギング10×10マックスパワーPE X9 の1.5号を使用しています。
選んでいる一番の理由は感度の良さです。この釣りでは感度が本当に重要。最優先事項です。
確実に底を取ることが第一ですからね。とにかく底を取る。
いかにして底を取るかということが、まずこの釣りの最大の特徴というか、最重要テクニック。
底が取れた瞬間の立ち上がりの速さも大切です。
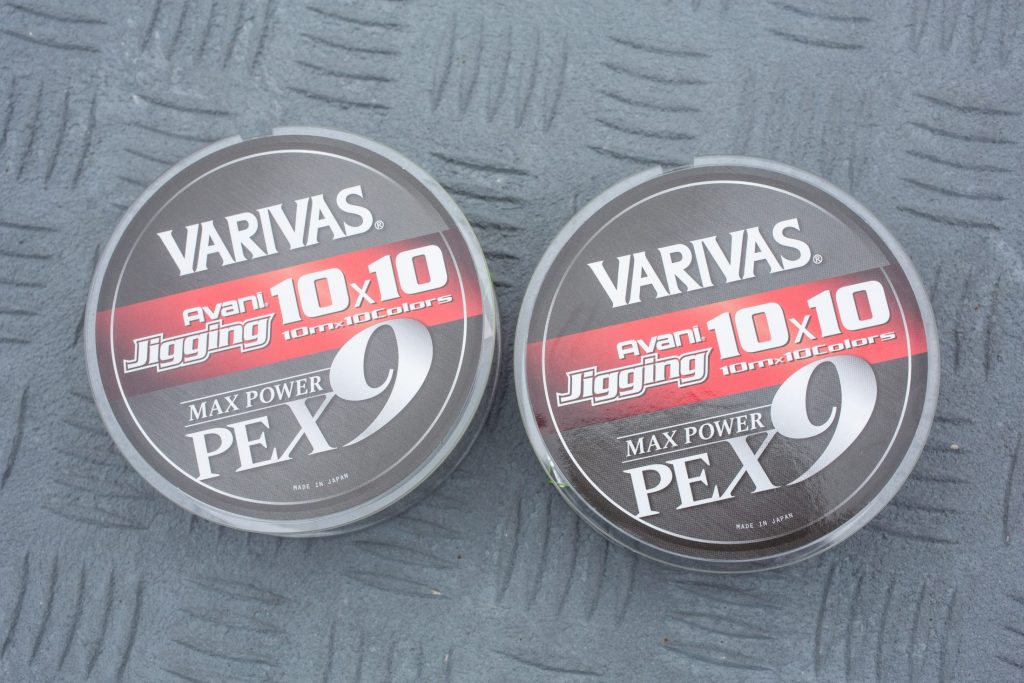
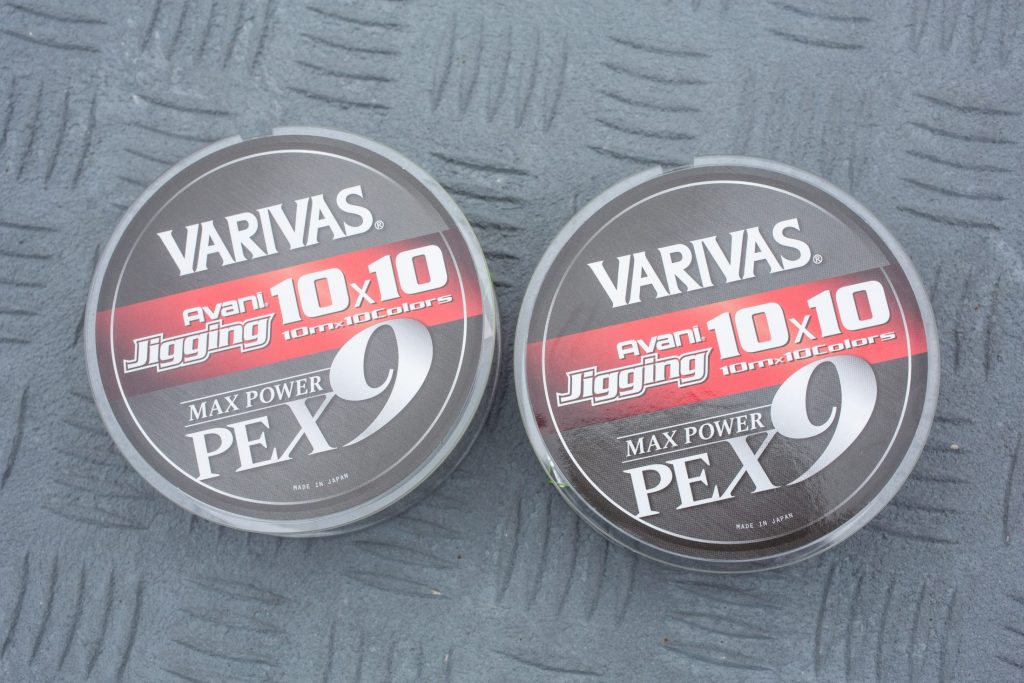
こうしたテクニックを詰めていくと感度はもちろん、水を切るという性能も重視するようになります。
タイラバを落とすとき、糸フケをなるべく出さず、真っすぐに落ちて欲しい。
これはPEラインの直進性や水切り性能の問題になってきます。
もちろん、複雑な潮で二枚潮、三枚潮のときにはいくらジギング10×10マックスパワーPE X9の水切り性能がよくても1回の投入でスッと底を取ることは不可能なこともあります。
そういうときに「何ができるの?」っていうと、潮上に少し投げ込んで、途中で何回か止めて、何回かラインを真っ直ぐにして落としたりするテクニックが必要になったりします。
こうしたテクニックを駆使して落とす、という状況では水切りが良いPEラインと水切りが良くないPEラインの差はハッキリと出てきます。
真っ直ぐにできないんですね、水切りの悪いPEラインは。
ジギング10×10マックスパワーPE X9ならこのテクニックが思い通りに使えます。
ヘッドの重さとPEラインの水切りの良さ、直進性を利用して、真っすぐにタイラバを落としていくことが出来るんです。


強度や耐久性についてはいかがですか?
ジギング10×10マックスパワーPE X9に関しては、強度はまったく問題ないですね。
ひと昔前のラインに比べるとワンランク上がった強さと耐久性があります。
なかなか劣化もしないし、色落ちもあまりしない。
このあたりの基本性能は当然高い、という感じです。
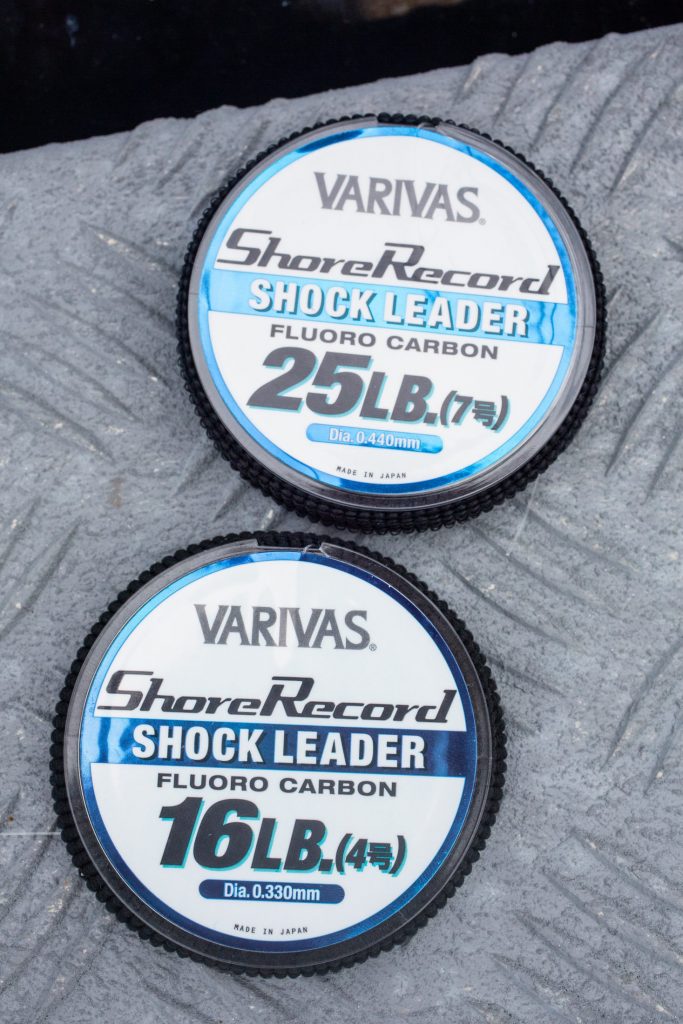
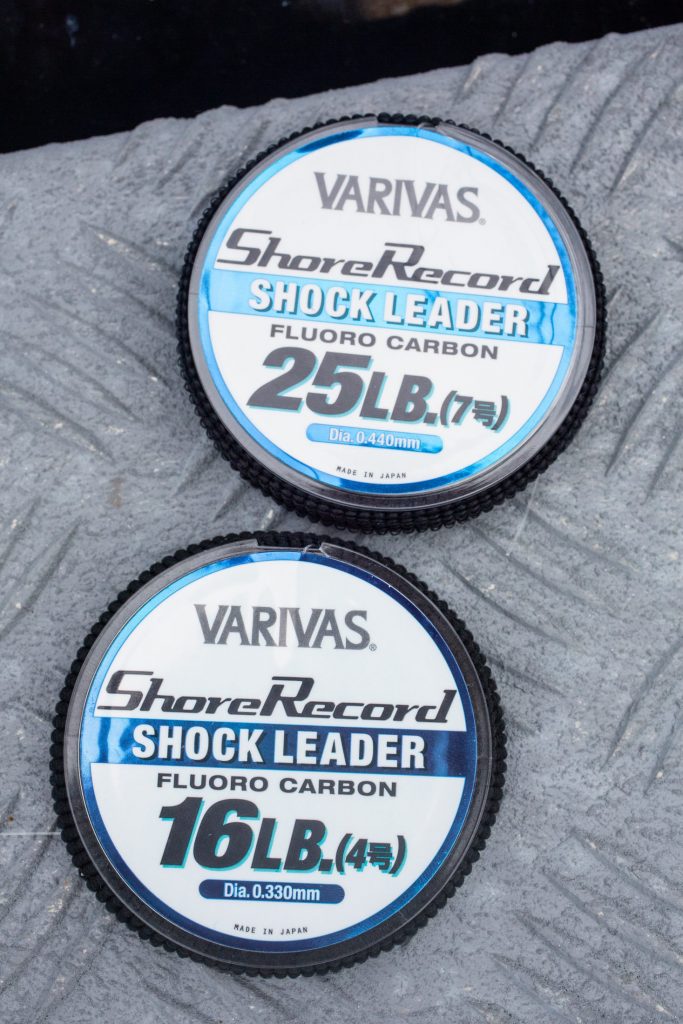
ショックリーダーについてはいかがでしょう。
使用しているのはバリバスのショアレコードショックリーダーです。
このショックリーダーは何より結節が強い。
根掛かりした時にどれだけ強いか、ということがよく分かります。切れないんです、なかなか。
今年の春にリリースされたばかりのショックリーダーなので、それほど長期間使っているわけではないんですが、明らかに違いを感じますね。
根ズレや魚体ズレに対する、いわゆる耐摩耗性はショックリーダーに必要な最低限の要素として、なくてはならないものです。
ショアレコードショックリーダーに関しては十分だと感じています。
繰り返しになりますが、これまでのショックリーダーと比較して、一番違いを感じる点はノット強度です。
僕はこの釣りでは、根掛かりしたらノット部分で切れるよう、少し結節強度が劣るオルブライトノットを使って結節しています。
それでも切れるときの感覚、力の加減からしてやはりノット強度はすこぶる高いと感じます。


根掛かりさせないことが第一ですが、それでも根掛かりは避けられないのが海峡マダイです。切ることを前提にしたリーダーシステムを使用しているということですが…。
PEラインと結節するショックリーダーは12~16lb。3mほどセットします。
その先にスナップスイベルを結びます。先端には25~35lbのショックリーダーを70~80cmセットします。
スナップスイベルとはスイベルで接続します。
先端のショックリーダーが太いのは根ズレ対策、魚体ズレへの対応です。タイラバを含めた各部の結節はダブルクリンチノットを使っています。


根掛かりして切るしかない、となったときにこのシステムならスナップスイベルに結んだショックリーダーの部分で切れます。
最悪の場合でもPEラインと細いショックリーダーのオルブライトノットの部分で切れます。
PEラインが高切れすることはありません。
切りたいところで切るためのシステムです。スイベルを2つ入れているのでヨレにくく、強度が落ちにくいところも特長ですね。
海峡マダイを狙うための佐藤偉知郎流タックル|タイラバ
使用しているタイラバについて教えてください。
タイラバはダイワの紅牙ブランドの各製品をいろいろ使っています。ウエイトは150gから300gを使用しています。
ヘッドの素材は鉛を中心にタングステンも使っています。
タングステンのヘッドは高価なのが難点ですが、底が取れない時は少しでも速く落ちるものの方が取りやすいので使うときもありますね。
タングステンヘッドを使う場合はネクタイやフックとかはこじんまりさせています。
鉛はヘッド自体も大きいので、フックも少し大きくして存在感があるようにしています。要はバランスの問題です。


ネクタイについてのこだわりはありますか?
ネクタイの素材とか形状は釣果に差が出る気はしますね。
紅牙タコマラカスベイトみたいなワームと普通のネクタイ系ではっきり差が出るときもありますしね。
動きが大きい方がいい時は徹底して大きい方がいい。反対に大きい動きがダメな時もある。
この違いはベイトの種類の問題だと思います。
あとはマダイの数。やっぱり数がいれば、競争原理が働いて、食いやすいと思いますし。


タイラバのヘッドやネクタイのカラーの使い分け、好みなどはありますか?
ないです。全然ない。僕の気分です。
だけど、使っていてアタったりすると、使い続けたくなりますよね。
まあ、心の問題ですよね(笑)。
カラーについてある程度バリエーションを持っていて、その日に合うやつを気分でローテーションする、というくらいですね。


フックは要チューニングということですが…。
フックはノーマルのセッティングではなく全部手を入れています。
サイズをデカくすることがメインのチューニングです。小さいと折られちゃうんですよ。
青物が掛かることも多いので、弱いフックだと一瞬でヤラれてしまいます。本数も増やしています。
ダイワの純正品は2本ですが、これに1〜2本追加して3本か4本にしています。
追加するフックはサイズアップして、段差をつけて散らしています。
タコベイトに関してはフックサイズはすべてデカいやつです。16番、17番とかを3〜4本つけてますね。
フックの本数を増やす理由は、フッキング率を上げるためというより、どちらかといえばバラシ防止の意味が大きいですね。
佐藤偉知郎流・海峡マダイ攻略術


海峡マダイを攻略するために、一番重要なことはどんなことですか?
底を取ることが最重要ですね。
タイラバが着底してもラインの出が止まらないことも多いんです。ラインの放出が止まれば着底は分かりますよね。
でも、止まらないことも多いのが海峡マダイの特徴です。
対応策としてラインが放出されるスピードを常に凝視しておくことが大切。スピードが変わった瞬間が着底という感じです。
1回は取れても2回目は取れない、ということもよくあります。
そんなときは取れていることを前提として巻き始めることもあります。
もう着いているだろうという想定でやらないと、根がかりしてしまいますので。
着底から10mくらい上げてきて落とし直したとき、5mくらいしかラインが出ないようなら、それを想定したラインの量を出せばいいですが、下手すると20mぐらい出る時もあるわけです。
もう、そうなってくると、もう勘でやるしかないですね。1回も底が取れない時とかも結構ありますからね。


巻き上げについてのアドバイスはありますか?


タイラバって超スローに巻いているイメージがあるかも知れませんが、それだけではないことに注意してほしいですね。
毎回といっていいくらい潮が流れるスピードが違うので、巻いてくるタイラバの動きもどんどん変えていかないとダメです。
着底してから上がってくる、タイラバのスピードや軌道のイメージを持てるかどうかの違いはすごく大きい。
とにかく状況が刻々と変化するので、スタンダードにしていることはあまりないんです。その時々ですごく幅広く変えています
釣れるんだったらそれはそれでいいかなと思いますが、速い流れのなかで理想的なスピードで泳がせるためにはどうすればいいかを常に考えています。
止めて巻かないときもありますし、巻かずにラインを出していくこともあります。
つまりは理想的なスピードを出すための作業なんです。


佐藤偉知郎流・海峡マダイについての目標
海峡マダイで目標としていることはありますか?
釣り方としてはある程度成熟しているので、あとは自己記録をどんどん更新できればいいかな、と思います。
90cmオーバーは何本か見ていますが、メーターオーバーも確実にいると思っています。
そういう夢のサイズがいる海域なので、取れればいいなっていう思いはあります。夢かもしれないですけどね。ロマンはありますよね。
佐藤偉知郎使用・海峡マダイ用タックル
佐藤偉知郎さんが使用している海峡マダイ用タックルをご紹介。
タックル1
| タックル | 詳細 |
|---|---|
| ロッド | ソウルズ/ タイブレーク60SF-TB60LC |
| リール | ダイワ/ ソルティガIC100P-DH |
| PEライン | 【バリバス】 アバニ ジギング10×10マックスパワーPE X9 1.5号 200m |
| ショックリーダー | 【バリバス】 ショアレコードショックリーダー フロロカーボン 12~16lb+25~30lb |
タックル2
| タックル | 詳細 |
|---|---|
| ロッド | ソウルズ/ タイブレーク60SF-TB60LC |
| リール | ダイワ/ ソルティガIC300-DH |
| PEライン | 【バリバス】 アバニ ジギング10×10マックスパワーPE X9 1.5号 300m |
| ショックリーダー | 【バリバス】 ショアレコードショックリーダー フロロカーボン 12~16lb+25~30lb |


バリバス スタッフ使用タックル
| タックル | 詳細 |
|---|---|
| ロッド | テールウォーク/ タイゲームSSD C61XXH/FSL |
| リール | ダイワ/ ソルティガIC100-DH |
| PEライン | 【バリバス】 アバニ ジギング10×10マックスパワーPE X9 1.5号 200m |
| ショックリーダー | 【バリバス】 ショアレコードショックリーダー フロロカーボン 12~16lb+25~30lb |






